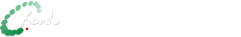【1385】 義務を果たすから権利が成立する~権利と義務は社会契約~
先日、電車で向かい合わせの席に座っていたときに、
若手男性3人のサラリーマンが「休む権利」について話していました。
おそらく大学の同級生で、久しぶりに飲もうということになったようです。
1人が何らかの大きなプロジェクトに関わっていて、なかなかそれが進捗せずに
同僚も含めて、長く休んでなく、疲労とストレスが溜まり、
その日は仮病を使って「病欠」にし、友人と飲んだようです。
私は目を閉じ、窓にもたれかかって寝たふりをしながら聞いていたのですが、
彼らが電車を降りるまで、一度も「義務」の話をしませんでした。
「権利」は単独で存在するものではなく、人と人、もしくは社会との関係性の中で成立します。
スコット・ハーショヴィッツ氏が「父が息子に語る 壮大かつ圧倒的に面白い哲学の書」の中で
次のように語っています。
*********************************************************************
権利は手で持てるものではない、というのは正しい。
権利はだれかの中ではなく、関係性の中に存在するものだからだ。
その意味を説明しよう。
あなたが私に1000ドル貸しているとする。
あなたには私に1000ドル請求する権利がある。
その請求権は私に対するもので、あなたがお金を貸しているのが私だけなら、
私に対してだけ有効な権利ということになる。
複数の人に貸しているなら、請求権は複数の人に対して存在する。
*********************************************************************
このとき「あなた」は請求する権利を持ち、「私」は返す義務があります。
このように、権利は他者との関係性の中で成立するものなので、
必然的に「義務」とセットになります。
わかりやすく幾つか事例をあげて説明します。
1.「表現の自由」
この権利を行使するのであれば「他者を不当に傷つけない」、
という義務を果たさなければなりません。
SNSでの誹謗中傷は、権利だけが行使されているように感じます。
2.「所有権」
この権利は、「他人のものを盗まない」、「契約を守る」という
義務とセットでなければ、世の中が崩壊します。
3.「労働者の権利」
この働く者の権利を主張するのであれば、
「職場のルールを守り、責任を果たす」ことが義務となります。
このように、権利は「もらうだけのもの」ではなく、
それを成り立たせるために誰かが義務を果たしているからこそ成立します。
ルソーは「社会契約論」で
*********************************************************************
市民は自由を持つが、その自由を守るために、共同体のルールを守る義務がある
*********************************************************************
と言っています。
権利を持つなら、それを支える義務を果たさなければならないのです。
冒頭の仮病で病欠した彼は、
労働者には「労働する権利(=労働力維持のための休む権利も含む)」があるが、
同時に「企業のルールを守り、責任を果たす義務」があることを忘れてはなりません。
さらに、企業には「利益を追求する権利(=プロジェクトを成功させる権利)」があるが、
同時に「労働者を適切に扱う義務(=休ませる義務)」があります。
お互いが権利を主張すると義務が宙に浮いてしまいます。
このバランスが崩れると、社会が機能しなくなります。
労働者も企業も
「誰がどのような義務を果たすことで、その権利が成立するのか?」
これを常に考えていただきたいと思います。
スコット・ハーショヴィッツ氏「父が息子に語る 壮大かつ圧倒的に面白い哲学の書」
★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★
本ブログはメルマガで配信されます。
ご希望の方は下記の登録フォームをご利用下さいませ。
https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=afspwg
★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★
☆★☆★☆★「オールインワン」コンサルティングのご案内☆★☆★☆★
●「経営者のメンター」
●「経営戦略の立案とその実行サポート」
●「成果に直結する管理職のマネジメント及びチームビルディング能力向上サポート」
●「働きがい、やり甲斐に繋がる組織・風土及び社員の人格作りのサポート」
●「営業やマーケティングの成果倍増アドバイザー」
これらが一つになったコンサルティングメニューがスタートしました。
これによって、御社の現場力を倍増させ、人財育成と業務成果を高めます。
また、上記から、重要度の高いものを選択して、経営改善するコースもあります。
詳しい内容は下記をご覧下さい。