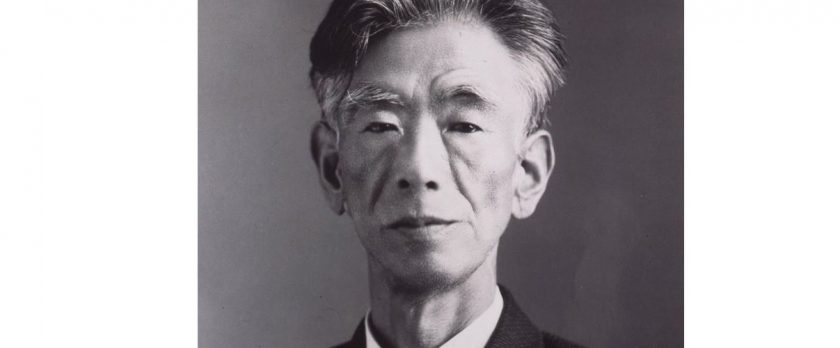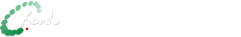【1389】 AIに勝つには「●●」を磨くのみ!~人間だけが持つ武器。岡潔先生が示した答え~
【1388 知ってる?頭の良さは情緒で決まるんだって~数学者・岡潔が示した“賢さの条件”~】
https://km.kando-m.jp/news/mm1388/
こちらの続編となります。
岡潔先生が語る「情緒」とは、
「物事を理屈ではなく、心で感じること」
を意味します。
先生は、人間の知性や創造力は情緒の上に成り立つと考えていました。
■情緒の具体的な意味は、次のように考えられます。
・論理や知識ではなく、心の働きで物事を感じること
・自然や芸術に対する感受性を養うこと
・日本人の精神文化において重要な役割を持つこと
たとえば、
・桜の花を見て「美しい」と感じる
・月を眺めて「物悲しい」と思う
・文学や詩から深い感動を受ける
こうした「感じる力」こそが、先生が重視する「情緒」なのです。
私は 満開の桜も好きですし、桜吹雪の美しさにも惹かれます。
しかし、一番好きなのは「葉桜」です。
「葉桜」は、桜の終わりと捉えられがちですが、私はこう思います。
「さぁ、来年の春にまた咲くために、今日からスタートだ」
まるで桜が、そう語りかけてくるように感じるのです。
このように感じることこそ、私にとっての「情緒」です。
そう言えば、二宮尊徳翁も
「元旦や 今年もあるぞ 大晦日」
という句を残しています。
これは一年の計は元旦にあり、ということですが、葉桜も同じと私は考えます。
■先生は、なぜ「情緒」が大切と言うのか?
先生は「数学の発見は、理屈ではなく“ひらめき”によるもの」と考えていました。
随筆の中で、先生の生いたちが詳細に記されていますが、
長年取り組んでも答えが出なかったことや新たな発見は、
その多くが、何かをしているときに“ふとひらめいた”ものだった といいます。
そのため、先生は「ひらめき」を大切にし、
ひらめきは豊かな情緒によって育まれるものだ と語っています。
知識や論理だけでは、深い理解や創造は生まれません。
人間が本当に賢くなるためには、情緒が育っていなければならないのです。
日本人は昔から、「四季の移ろい」や「詩歌」を通じて、情緒を育んできました。
松尾芭蕉の俳句などは、まさに“情緒の結晶” といえるでしょう。
しかし、現代では 理屈やデータばかりが重視され、
情緒を育てる機会が失われつつあります。
読書をやめ、ゲームやSNSに浸っていて、果たして情緒が育まれるのでしょうか?
これからの社会は、ますます AIやデータが中心 になっていくでしょう。
しかし、それによって 人間が「感じる力」を失ってはなりません。
人間らしい、クリエイティブな発想や直感を養うためには、「心の豊かさ」が不可欠です。
だからこそ、
「もっと情緒を大切にしなければならない」
と強く思います。
★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★
本ブログはメルマガで配信されます。
ご希望の方は下記の登録フォームをご利用下さいませ。
https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=afspwg
★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★
☆★☆★☆★「オールインワン」コンサルティングのご案内☆★☆★☆★
●「経営者のメンター」
●「経営戦略の立案とその実行サポート」
●「成果に直結する管理職のマネジメント及びチームビルディング能力向上サポート」
●「働きがい、やり甲斐に繋がる組織・風土及び社員の人格作りのサポート」
●「営業やマーケティングの成果倍増アドバイザー」
これらが一つになったコンサルティングメニューがスタートしました。
これによって、御社の現場力を倍増させ、人財育成と業務成果を高めます。
また、上記から、重要度の高いものを選択して、経営改善するコースもあります。
詳しい内容は下記をご覧下さい。