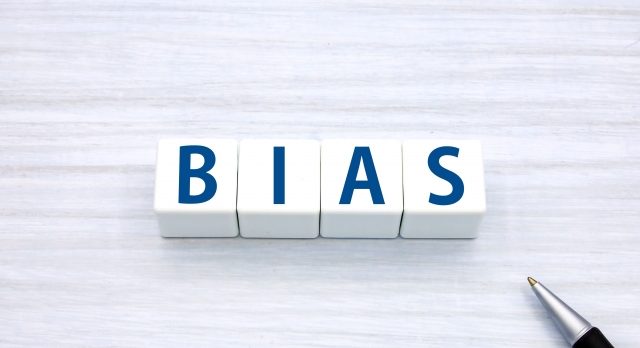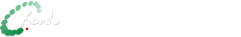【1418】 なぜ人は偏った憶測をしてしまうのか? 〜ケリーの自己奉仕的バイアスから学ぶ(1)〜
「うまくいったのは自分の努力、失敗したのは環境のせい」
※ここで言う環境には、上司の指示や同僚の協力なども含まれます。
こんなふうに、自分に都合の良いように原因を考えてしまうこと、ありませんか?
これは心理学で「自己奉仕的バイアス(self-serving bias)」と呼ばれるもので、
人が無意識に持ってしまう“思考のクセ”の一つです。
このクセが強い人とあまりそれを感じない人が皆さんの周囲にもいらっしゃいますよね?
皆さんが頷かれている姿が想像できます(笑)
このバイアスを理解するうえで欠かせないのが、心理学者ハロルド・ケリーの「帰属理論」です。
ケリーはアメリカの社会心理学者で、
UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)で長年教鞭を執り、
対人関係や社会的認知の研究で多くの功績を残した人です。
このケリーの唱えた「帰属理論」についてお伝えします。
人は、目の前で起こった出来事について、
「それは誰のせいか?」「なぜそうなったのか?」を考えるときに、
次の3つの視点をもとに判断していると言われています。
・一貫性:その人はいつもそうなのか?
・弁別性:その行動は特定の状況だけか?
・合意性:他の人も同じようにするか?
「弁別性って何?」と疑問を持たれた方もいらっしゃると思いますので、少し解説します。
弁別性(distinctiveness)とは、
「その人が、他の状況では同じ行動をしないかどうか」を見る視点です。
たとえば:
Aさんが「会議ではいつも怒る」けど、「プライベートでは穏やか」だとします。
この場合、Aさんの怒りは“会議”という状況に特有のもので、弁別性が高いとなります。
逆に、「どこでも誰にでも怒っている」ならば、弁別性が低いとなります。
つまり、「その行動が“どこでも起きるのか、特定の場面だけなのか”」を見て、
原因が人なのか状況なのかを判断する材料になります。
話を元に戻します。
皆さんの部下が会議に遅刻したとします。
この遅刻を「帰属理論」で整理してみます。
・一貫性あり:その部下は毎回の朝会で遅刻している
・弁別性なし:会議だけでなく研修や打合せでも遅刻している
・合意性なし:他の人は遅刻していない
このような場合、「本人の性格や習慣(内的要因)」が原因だと判断されやすくなります。
逆に、「たまたま電車の事故」「他の人も遅れている」などがわかれば、
外的な要因だと考えることになります。
今回は「部下の遅刻」で帰属判断をしましたが、部下の行動を捉え直すことで
指導のアプローチも変わってきます。
この理論による判断(=帰属判断)は現場でも非常に重要な視点だと思います。
次回は、自分自身に対する帰属判断について触れてみますね。
お楽しみに!
★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★
本ブログはメルマガで配信されます。
ご希望の方は下記の登録フォームをご利用下さいませ。
https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=afspwg
★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★
☆★☆★☆★「オールインワン」コンサルティングのご案内☆★☆★☆★
●「経営者のメンター」
●「経営戦略の立案とその実行サポート」
●「成果に直結する管理職のマネジメント及びチームビルディング能力向上サポート」
●「働きがい、やり甲斐に繋がる組織・風土及び社員の人格作りのサポート」
●「営業やマーケティングの成果倍増アドバイザー」
これらが一つになったコンサルティングメニューがスタートしました。
これによって、御社の現場力を倍増させ、人財育成と業務成果を高めます。
また、上記から、重要度の高いものを選択して、経営改善するコースもあります。
詳しい内容は下記をご覧下さい。