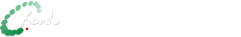【1478】 「満足」は誰のものか?~サティスファイスと日本品質~
1978年、認知科学者として初めてノーベル経済学賞を受賞したハーバート・サイモン。
彼の著書には「サティスファイス(satisfice)」という言葉が登場します。
これは「満足する=satisfy」と「十分である=suffice」を組み合わせた、彼の造語です。
そしてこの言葉は、「満足化原理(satisficing principle)」へとつながっています。
満足化原理とは、「最適な選択」ではなく、「十分に満足できる選択」を人は取るという考え方です。
この原理を知ったとき、私は強く実感しました。
「人の『満足』は、その人だけのものである」
車、ファッション、食事・・・、私たちの暮らしの中には数え切れない選択肢があります。
それを「満足」「普通」「不満」と判断しているのは、他でもない“その人”自身です。
私たちの経済は、商品やサービスを提供・消費することで成り立っていますが、
提供する企業側から見れば「自分が1」で相手は「多数の消費者」という構造であり、
一方、消費者から見れば「自分が1」で、相手は「多数のメーカー」となります。
つまり、「満足」の基準は人の数だけ存在し、
そのすべてを満たすことは、原理的に不可能と言えます。
それでも戦後の日本企業は、世界中の人々を満足させるために努力を重ねてきました。
その積み重ねが、「MADE IN JAPAN」という日本品質を世界に誇れるブランドへと育てました。
そこには、目に見えない凄まじい努力と誇りがあったに違いありません。
話は変わりますが、ある経営者がこう話してくれました。
「うちの社員は70~80%の出来で満足してしまっている」
「本人は“目一杯やった”つもりだが、正直物足りない」・・・・・・と。
ここにも満足化原理が働いています。
たとえ本人が全力を尽くしていたとしても、
その“全力の水準”が低ければ、社長の求めるクオリティには届かないのです。
皆さんの周囲にも、そんな「満足レベルの低さ」が気になる方はいませんか?
かつての職人や photographer(写真家)、designer(デザイナー)など、
「〇〇er」と呼ばれる人たちには、
自分の満足ラインを常人よりも高く設定していた人が多かったように思います。
「これでもか」と自らの技術を磨き続ける探究心。
大変そうだけど、幸福そうな顔をされていました。
ところが最近は、自動化やAIの進化により、
スキルを磨かなくてもある程度の水準を出せる時代になっています。
でも、そこで得た“満足”は本当に“幸福”と言えるのでしょうか?
そんな疑問が、ふと心に浮かびました。
■本日の教訓
「満足」は、他人の評価ではない。自分の水準が未来を決める。
★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★
本ブログはメルマガで配信されます。
ご希望の方は下記の登録フォームをご利用下さいませ。
https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=afspwg
★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★
☆★☆★☆★「オールインワン」コンサルティングのご案内☆★☆★☆★
●「経営者のメンター」
●「経営戦略の立案とその実行サポート」
●「成果に直結する管理職のマネジメント及びチームビルディング能力向上サポート」
●「働きがい、やり甲斐に繋がる組織・風土及び社員の人格作りのサポート」
●「営業やマーケティングの成果倍増アドバイザー」
これらが一つになったコンサルティングメニューがスタートしました。
これによって、御社の現場力を倍増させ、人財育成と業務成果を高めます。
また、上記から、重要度の高いものを選択して、経営改善するコースもあります。
詳しい内容は下記をご覧下さい。