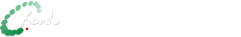【第809号】 「性質と性格」 変えられるものと変えられないもの
「性質と性格」どちらを変えることができるでしょうか?
このことを考える前に「性質と性格」の構造を理解しましょう。
中心にあるものは「気質」です。
その「気質」を取り囲むように「基本的人格」が形成され、
それを取り囲むように「習慣的性格(態度的性格とも言います)」が形成され、
さらにそれを「役割性格」が取り囲みます。
変えることができないのは、
気質(生まれつきの性格)と基本的人格です。
変化し、進化することができるのは、
習慣的性格(態度的性格)と役割性格です。
それぞれについて説明いたします。
「気質(生まれつき性格)」は遺伝的に引き継がれたこともあり、
後天的に変える事ができません。
「基本的人格」は、ほぼ幼少期に養育者(親など)の影響により確立されます。
三つ子の魂百までという諺がありますよね。
3歳くらいで、脳内神経細胞のおよそ80パーセントが完成され、
高等生物の特徴である厚い大脳新皮質はこの時期に作られます。
重要なのは「習慣的性格(態度的性格)」です。
これは人生を歩む中で形成される「人生哲学」的な性格です。
やると決めたことは必ず実行する。
1度や2度の失敗では諦めずに成果が出るまで続ける。
できない言い訳をしない。
こういう風に強く生きる人もいれば、
逆な人もいます。例えば
忙しかったらできなかったのも仕方がない
うまくいかなかったのは、○○さんがちゃんとやらなかったからだ
私も悪かったけど、○○さんも悪かったから、○○さんが先に謝るべきだ。
同じ様なことに向き合った際に、前者と後者では結果が違います。
結果はやる前に出ています。
何かに向き合った際にどういう選択をするか!
これを習慣的性格(態度的性格)と言います。
京セラの稲盛和夫氏は、「人格=性格+哲学」と言われています。
氏の言われる性格は「気質」と「基本的人格」であり、
哲学が「習慣的性格(態度的性格)」になります。
人生で形成される性格はさらにもう一つあります。
それが「役割性格」です。
人は、会社や家庭、友人関係、地域など様々な場面で
それぞれの役割を担っています。
会社では経営者であっても、家に帰れば家長であり、父、夫、PTAの役員など
日常生活の様々な環境に適応するために、
果たすべき役割にあった性格を使い分けます。
人は年を重ねるにつれ適応しなければならない環境が増えます。
さまざまな役割性格を使い分けることは、
社会に適応していくための大切な技術となります。
このように一見一つに見える人格も
大きく4つに分類できることを知っておくと
自分も含めて「人」がよく見えてきます。
生まれながらの気質と基本的人格のみで生きている人はほとんどいません。
みんな何らかの努力で人格を作っているのです。
☆★☆★☆★「オールインワン」コンサルティング☆★☆★☆★
●「経営者のメンター」
●「経営戦略の立案とその実行サポート」
●「成果に直結する管理職のマネジメント及びチームビルディング能力向上サポート」
●「働きがい、やり甲斐に繋がる組織・風土及び社員の人格作りのサポート」
●「営業やマーケティングの成果倍増アドバイザー」
これらが一つになったコンサルティングメニューがスタートしました。
これによって、御社の現場力を倍増させ、人財育成と業務成果を高めます。
また、上記から、重要度の高いものを選択して、経営改善するコースもあります。
詳しい内容は下記をご覧下さい。