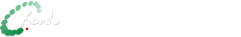【1469】 経営は「生きた芸術作品」である~松下幸之助~
先日、2代目経営者として就任された、比較的若い方から「経営者の心得を教えてほしい」と尋ねられました。
私自身、人に心得を語れるほどの経営をしているわけではありませんが、
その場では松下幸之助翁の『実践経営哲学』にある一節を要約してお伝えしました。
その方は私のメルマガにも登録してくださったので、
「いずれ全文をご紹介します」と約束していたのですが、
本日はその機会として、該当箇所をそのまま掲載させていただきます。
経営者に限らず、日々の仕事に誇りと覚悟を持つすべての方にとって、
きっと何かのヒントになるはずです。
********************************************************************************
一枚の絵でも、その出来、不出来によって価値に大きな違いがある。
経営もそれと同じことであるが、ただ絵の場合は、それが駄作であっても、
人々に感動を与えないというだけで、迷惑を及ぼすということはない。
しかし経営の駄作はそうではない。
関係する各方面に多大の迷惑をかけるのである。
いちばんはなはだしい例としては、倒産、破産ということを考えれば、
経営の駄作、失敗作がいかに社会にとって好ましくないかが分かるであろう。
その反対に、芸術の名にふさわしいような真に立派な経営は社会に益するところがきわめて大きいのである。
だから、経営の芸術家たる経営者は、一般の芸術家の人々以上に、
芸術的な名作を生み出す義務があるといえよう。
私は芸術のことはよくは知らないが、伝え聞くところによれば、
芸術家が一人前になるための修業というものはきわめて厳しいようであり、
また一つの作品の制作に取り組むときは、
文字どおり骨身をけずるような思いで全身全霊を打ちこむということである。
そのようにしてはじめて、人々を感動させ、後世に残るような芸術作品が生まれるわけである。
そういうことを考えると、生きた総合芸術である経営の名作をつくるためには、
それに劣らぬ、あるいはそれ以上の厳しい精進、努力が求められてくると考えなくてはならない。
そういうものなしに経営の成果をあげようとすることは、
普通の努力だけで何百万円もする名画を描こうと考えるのと同じで、
うまくいくわけがないことははっきりしている。
経営は生きた総合芸術である。
そういう経営の高い価値をしっかり認識し、その価値ある仕事に携わっている誇りをもち、
それに値するよう最大の努力をしていくことが経営者にとって求められているのである。
********************************************************************************
要約すると、
「経営は、社会に大きな影響を与える『生きた総合芸術』である」
と言えます。
経営者でなくても、自分の仕事の成果は“駄作”であってはなりません。
皆さんの提供する商品やサービスには、対価を払ってくださる方がいます。
その方々に対価以上の価値を提供する“秀作”で応える必要があります。
つまり私たちは、芸術家と同等の覚悟と精進が求められるのです。
安易な姿勢では、価値ある成果は決して生まれません。
■本日の教訓
経営とは、社会に貢献する“名作”を生み出す行為。志と努力なくして成果なし。
実践経営哲学のお求めはこちら