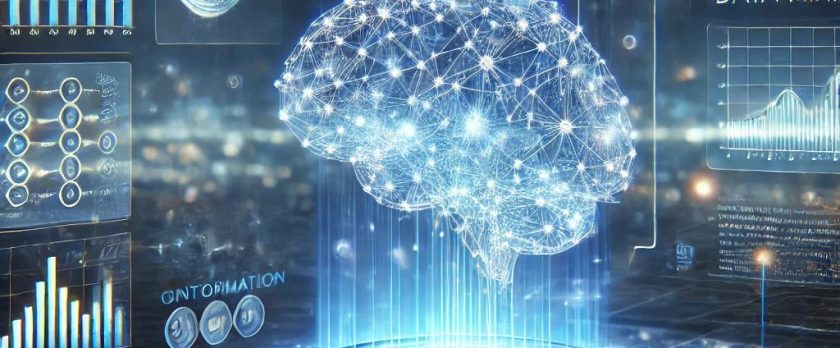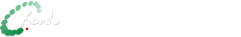【1392】 「検討します」の商談、多いですよね?~その中から“成約の種”を見つける方法~
営業の新規開拓の際に、訪問先での会話をTeam Managerの商談履歴に残します。
はっきりと「必要ありません」と言われると諦めがつくのですが、
「後日機会があったらお願いします」という肯定とも否定とも取れる
曖昧な返答が非常に多いのが現実です。
あまりに多いため、いちいち商談履歴に残すのが面倒と思われている営業担当も多いと思います。
二度と日の目を見ない商談履歴であれば、それは営業資産とは言えません。
顧問先の日々の多数の商談履歴を見ていて、その営業努力を無駄にしたくない、
どうすればその資産を有効活用できるだろうか?
と考えたところ、データマイニングを生成AIに任せてはどうか?という考えが浮かびました。
次のような答えが返ってきたので、私の補足を加えて解説します。
1.データのパターンを分析
商談の履歴を確認し、以下のような曖昧な表現のパターンを抽出します。
・「また機会があれば」
・「後日連絡します」
・「前向きに検討します」
・「社内で相談してから」
・「タイミングが合えば」
・「ちょっと今回は見送りですが、またぜひ」
・「予算が確保できたら」
・「今は難しいですが、いずれ」
これらのように
「完全に否定ではないが、次につながる可能性がある」
言葉を含む商談をピックアップします。
2.可能性がある商談を絞り込む
・ピックアップした商談を時系列にリスト化する
・商談先ごとに「次回のフォロー推奨度」を付ける(例:3段階評価)
「次回のフォロー推奨度」を付ける作業が手作業ではとても難儀です。
そこで生成AIのデータマイニング技術(※1)を利用します。
(※1:大量のデータからパターンや関係性を発見し、有益な情報を抽出する技術)
・「後日機会があれば」と言われたが、以前に何度も同じ対応をされている。
これは、具体的な検討に進んでいない可能性が高く、有効商談の可能性は低いと判断されます。
・「社内で検討する」と言われたが、以前に同じ理由で断られたことがある。
これは、「検討しても良い」という印象を受けたということですが、
実際には検討していない可能性もあるので、有効商談としては中程度と判断されます。
・「来期予算が確保できたら」と言われた。
これは、予算の確保が成約のカギになるため、適切な時期にフォローすれば成約の可能性が高い。
したがって、有効商談としては高いと判断されます。
このように、相手の過去の対応や現在の状況に応じてフォローの優先度を決めるということです。
では「次回のフォローアクション」はどういうことをすれば良いでしょうか?
・リマインド
一定期間後に「状況はいかがでしょうか?」とメール・電話をします。
・追加提案
相手の検討を後押しするために、新しい情報や事例を提供します。
・上位決裁者へのアプローチ
「社内で検討中」と言われた場合、決裁権を持つ人物と直接話せるように働きかけます。
・次回アポイント設定
相手が前向きな場合、次回の打ち合わせ日を決める。
・特定の時期に再アプローチ
「予算が確保できたら」と言われた場合、予算決定時期を確認し、その時期にフォローします。
私が営業マネジメント職だった頃は、このすべてを行っていました。
そのため高い新規獲得率を誇れたと思います。
重要なのは「必要ない」と塩対応されないことです。
そのためには、事前のリサーチが重要で、
訪問先企業に自社のどのサービスを提供すると相手先にどんなメリットがあるか?
これを考えた上で新規開拓をすることが大切です。
そして、訪問した時には
上記の「次回のフォローアクション」ができる状況で商談を終えることが理想です。
本メルマガのような考え方を適用することで、
単に商談リストを眺めるのではなく、効率的にフォローを行い、
成約につながる可能性を最大化できます。
Team Managerと生成AIのコラボに新たな可能性を見つけることができました。
★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★
本ブログはメルマガで配信されます。
ご希望の方は下記の登録フォームをご利用下さいませ。
https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=afspwg
★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★
☆★☆★☆★「オールインワン」コンサルティングのご案内☆★☆★☆★
●「経営者のメンター」
●「経営戦略の立案とその実行サポート」
●「成果に直結する管理職のマネジメント及びチームビルディング能力向上サポート」
●「働きがい、やり甲斐に繋がる組織・風土及び社員の人格作りのサポート」
●「営業やマーケティングの成果倍増アドバイザー」
これらが一つになったコンサルティングメニューがスタートしました。
これによって、御社の現場力を倍増させ、人財育成と業務成果を高めます。
また、上記から、重要度の高いものを選択して、経営改善するコースもあります。
詳しい内容は下記をご覧下さい。